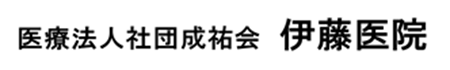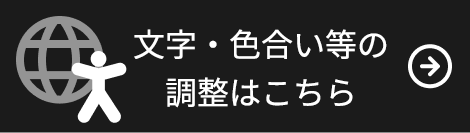- HOME
- 泌尿器科
このような症状はありませんか?
- 排尿回数が増える
- 夜中に何度もトイレに起きる
- 尿意があるのに尿が出にくい
- 尿を出し切れた感じがしない
- 尿漏れ
- 尿に血が混じる
- 排尿時に痛い、かゆい
- 排尿時の違和感
尿路感染症(尿道炎、膀胱炎、前立腺炎、精巣上体炎)
尿の通り道である尿管、膀胱、尿道に起こった、細菌感染(大腸菌、腸球菌、緑膿菌など)による炎症性疾患を総称して尿路感染症(UTI:urinary tract infection)と呼びます。尿路感染症は体の構造上、女性の方がかかりやすく、繰り返す方も多くいらっしゃいます。
尿路感染症の多くは排尿時の痛み、排尿時の違和感や残尿感、頻尿などの症状を認め、場合によってはご自身で認識できる尿の色の変化がみられることもあります。
男性特有の前立腺、精巣上体などの細菌感染症は尿路感染症とは本来は区別されるものですが、関連することも多いのでここでは同様に上記に含めさせていただきます。
前立腺炎、精巣上体炎は排尿時の痛みなどに加えて、性交時の痛みや、射精痛がみられることもあります。
尿路感染症全般に対して、当院では即時的にわかる尿検査キットにて、細菌感染があるかをまず簡易的に判断のうえ、症状に応じて、精密検査(尿細菌培養・同定検査)および抗菌薬の処方を行います。
過活動膀胱
膀胱が異常に収縮したり、知覚過敏になったりすることで、昼夜を問わず、突然の我慢できない尿意を感じたり(尿意切迫感)、さっき行ったばかりなのに何度もトイレに行ったり(頻尿)、トイレに間に合わず尿もれしてしまう(尿失禁)などの症状を伴います。
20歳台から発症する方もおり、一般的には40歳台から生じてきます。40歳台だと、7人に1人、80歳台以上だと3人に1人の割合で発症しています。
脳血管障害(脳卒中や脳梗塞など)や他の脳疾患、また脊髄損傷などが原因で脳から膀胱への信号に障害を来たしてしまう場合や、脳は関係なく、加齢や、前立腺が肥大することで(男性の場合)、過活動膀胱になったり、出産によって(女性の場合)、膀胱・子宮・尿道などを支えている骨盤底筋群が弱くなることで過活動膀胱を発症することがあります。
治療の基本は膀胱の機能を改善させるための薬剤は内服していただく必要がありますが、それとあわせて、骨盤底を支える筋肉の力を高めることや(骨盤底筋運動)、は、尿を我慢することで尿を膀胱に溜めておく機能を改善させる(膀胱訓練)ことも有用な場合もあります。
前立腺肥大症
前立腺肥大症は主に50歳以上の男性に見られ、加齢に伴い、前立腺の内側の細胞(内腺)が増殖しやすくなることが指摘されています。前立腺という臓器は膀胱の下に位置し、尿道を取り囲んでいるため、前立腺が肥大することで、尿の通路を狭めてしまうことになります。そのため、尿が出にくくなることで、「トイレで尿が出るまでに時間がかかる」、「尿の勢いが弱い」、「尿を出したくても出せない」、「排尿後なのにまだ残っている感じがする」、「夜中に何度もトイレに起きる」、などの症状が生じます。
前立腺肥大症の治療は、まず飲み薬での治療をはじめ、薬の効果を確認しながら、薬物療法で効果が不十分な場合には手術を検討することが一般的です。
陰部ヘルペス
陰部ヘルペスは性器ヘルペスともいわれるように、男女ともに性器の周囲に、違和感やピリピリとした痛みと共に赤く腫れた、小さな水疱(水ぶくれ)がまとまって出てきます。疲労、ストレス、体調不良など、免疫力が下がっているときに出てくることが多いため、からだを安静にしていただくことが大切です。ヘルペスウイルスの種類による感染症ですので、治療としては抗ウイルス薬を飲んでいただくことが多いです。陰部ヘルペス(性器ヘルペス)を何度も繰り返す方には、抑制療法として継続的に少量の抗ウイルス薬を飲み続けていただく場合もあります。